RRR | Ryogoku Rakuen Room | 両国楽園部屋
 >
その他 > インプロヴィゼーションについてのワークショップ
>
その他 > インプロヴィゼーションについてのワークショップ
インプロヴィゼーションについてのワークショップ
インプロヴィゼーションについてのワークショップ
講師:村山政二朗
通年で行う、ノンイディオマティックインプロヴィゼーションについてのエクササイズです。
日時:
第8回目 7/14(日)13:00-18:00
第9回目 7/28(日)13:00-18:00
第10回目 8/4(日)14:00-19:00
第11回目 8/25(日)13:00-18:00(最終回)
参加費:1日2,000円 (お申込:niiewsr@gmail.com )
音を使ったエクササイズが中心ですが、それ以外のことも行います。
インプロヴィゼーションということに本当に関心があれば、演奏経験の有無に関わらず、誰でも参加できます。
回を重ねていく中で、参加者が共同でなにか作品のようなものを作ってみてはどうかと思っています。 (この試み自体がノンイディオマティックには矛盾したものですが)
村山政二朗
打楽器奏者。
80年-90年代、灰野敬二、KKNULL、細田茂美等と共演。
1999年よりパリを拠点としヨーロッパで活動。
>>idioms and idiots ( with ray brassier, mattin, jean-luc guionnet )
http://www.seijiromurayama.com
【 第8回目のワークショップの結果を受けて 】 … 村山政二朗
観客の応援は音として大きくても、その内部で試合をしている選手たちの間には、各人の集中ゆえのサイレンスが存在し、それが聞こえてくる。
また、試合の主役である投手と打者、それぞれのサイレンスは、状況により安定と不安定のはざまでその質を変化させる。
そのサイレンスが深ければ、選手にはスタンドからやって来る音は聞こえていないだろうし、そのサイレンスが不安定な場合、「外野」の騒音、罵声は耐え難いものとなるだろう。
解説があると、いちいち自分で見てわかろうとしなくなる。それだけでなく解説が見えなくするものもある。
解説は理解を助けるが、そのマイナス面もある。すくなくとも、解説音声をつけたり消したりできる選択があるのはよい。
解説がない時の、いわば色付けされていない生の野球を見て(それはもちろん実際の観戦とも違うが)、改めて選手たちのプレーの凄さに自分の想像力が追いつこうとしていく(プロではパッとしない選手もそれなりのレベルに達しているのだ)。解説を聞いて野球がわかったような気になって、いつのまにか細部が見えなくなっていた。イディオマティックによって、ノンイディオマティックな細部がカモフラージュされていた。
コトバの両面。プラスとマイナスと。
特にその暴力に対しては用心する必要がある。それに対して免疫がない人には気を配らなくては。そうでないと、コトバがもとで死んでしまう人がいる。
その場合も、「真剣に生きた」という事実はあるだろうから、それはそれで仕方がないと言えようが、その死んでしまった人が、自分の置かれていた苦しい状況から逃れ、別の状況の中に自分を置く可能性を試せなかったのはもったいない気がする。
ただ、それぞれの人の置かれた状況は異なり、一概に語るのは難しい。
命の危険を感じたら、無理な状況からはエスケープするしかないが、エスケープばかりというのも自分で自分に無理な状況を作る。
「状況」対「自己」という対立する構図ができてしまうとそれが問題で、そうなるとこの構図から逃れるという選択が出てくるが、この構図が成立しないよう「自己」を変容させるという選択もありかと思う。自己からのエスケープ。
そうでもしないと、自分で気持ちのコントロールが利かなくなって、耐え難い状況の中で投げなければならない球、そのコントロールが利かなくなる。
自らが作り出す苦しい状況というものは、いろいろな言語ゲームをそのルールを守ってあまりにもきちんとやろうとすること、あるいはコトバにとらわれてとんでもない勘違いをすることが原因では?
例えば、「義務教育」というコトバも勘違いされやすく、親の義務であって子供の義務ではないのだというところがうまく伝わらない。小、中学校は行きたくなければ行かなくていいのだ。
エスケープして元気になれれば言語活動、イディオマティックの良さも見えてくる。最低限のエスケープは自分だけの時間を確保して何もしないことかと当初は思ったとしても、それができるということこそ贅沢だとあとで思い直す。
ノンイディオマティックインプロヴィゼーションというのはそういうエスケープを可能にする領域のはず(なのにうまく使われていないという印象。「自由」の履き違えがその理由か?)。
(だからと言ってやれば何でもいいとしてしまったら、積極的、生産的なエスケープでなくなる。それならそれで戦略が必要だ。)
イディオマティックの語源にはもちろんイディオムがあり、さらにそのもとにはイディオット(馬鹿)がある。与えられた条件に従って、馬鹿になって、夢中になってあることをする。
イディオマティックとノンイディオマティックという二つの分け方。このざっくりとしたわけ方でいろいろなことがわかりやすくなるし、実際両方が不可欠であることを考えれば、自分なりのバランス感覚をみつけることがよいだろうと考えてきたが、最近はそれはどうかと思うようになった。
結局、イディオマティックな性向のヒトとノンイディオマティックな志向も持つヒトの二類型があるのではないかということ。もちろん、イディオマティック派が主流という状況である。イディオマティックが社会のシステムを成立、維持させる。こういう時にはこうするを決め、そういうものがないと人間は途方に暮れてしまうことを考えれば、彼らが主であるということは誠に有り難いことだ。
問題はそれだけでは足りないということ。自己を対象化して見ようとしない限り片手落ちの危険がある。それだけでは足りないのみならず、それだけでは本当にイディオになってしまう。この意味で、ノンイディオマティックはイディオマティックにとって必要不可欠な要素である。そして逆も真なり、である。
自己を対象化してみるよい方法、その一つは例えば、母国語の通じない場所に行って、コミュニケートしてみようとすることである。未知の環境でのコミュニケーション能力習得のプロセスの困難さの中で、どれだけ自己というものが揺らぐか、それはひとたび海外に出てみればすぐに経験できる。
一つの外国語を身につけるプロセスというのは複雑である。それをたいした苦労なくやることができたと言える人は、その言葉の世界に入っていく楽しさが先に来て、困難な過程が忘れられたか、幸せなことにそれほど気にならなかったのだろう。
そのプロセスは複雑であるから面白い。その経験をもとに自分の母国語の体験を対象化できるから役立つ。
いずれにせよ、その学習過程で書物は役に立つ。イディオマティックなことをイディオマティックに学ぶ。実際は動的なものとして存在している事象を分析、統合の結果得られたいわゆる文法、この静的なものから始めるというのが無難であると一般的に考えられているが、のちのち発生する困難の芽もここにあると思う。動的なものを静的なものとするすり替えである。
本来はノンイディオマティックなものであるものをイディオマティックなものとしてイディオマティックなやり方で学ぶというわけだ。あれ、外国語は曲がりなりにも言語であるから、イディオマティックなのでは?という疑問がここで生じて当然だが、何がどうなっているのか未だわからないものに対峙する不安定な手さぐり状態という事態ゆえに、それはノンイディオマティックな事態であると言いたいのだ。そのような状況はたちまちコミュニケーション不能の事態に突入する可能性を秘めており、そんな状況にいることはまったくイディオ(馬鹿げた)なことだ。普通はそんなことをわざわざする必要はない。ただ、ある日そうなってしまった自分に気がつく、というわけだ。
もとい。
本来はノンイディオマティックなものであるものをイディオマティックなものとしてイディオマティックなやり方で学ぶ、このプロセスがすり替えであり、そこに困難のもとがある。
具体的な例。外国語学習の最初の困難のひとつは聞き取りである。音声を文字に変換するのは初学者にとって容易なことではない(「必要は母」ゆえの仏英伊使用者にこのトピックを語ること許されたし)。
聞き取りのエクササイズは流通している外国語教材の多くに含まれている。ただ、親切過ぎて、本当の親切にならない例だ。
本当の親身とは、急がば回れで、使う言語を一つにすることだ。日本語を解説では使うとしても、できるだけ省くようにする。たとえば、聞き取るべき音声のタイトル、順番などを伝えるために日本語が使われているのであるが、全く些細なことに見えたとしても実際はこれが大きなマイナス要素である。なぜか?日本語と外国語との往還をしなければならなくなるから。いちいち頭が変換をしなければならないから。その二つのテリトリーの移動がスムーズにできるなら、その時はすでに両方の言語使用者になっているはずである。
この事態はノンイディオマティックにイディオマティックな要素を混ぜ、わかりやすくするという意図から生まれるのだが、学習者はいつかそれによって動性を奪われていることに気づかねばならない。ただ、それに気づくには、そのような困難な経験を一通り巡ってみなければならないくらい、この局面におかれた人間はイディオマティックに従順なものである。
単純な話、音声ソフトを使い、いちいち日本語の部分を消去してみる。こうして、本当にエッセンスだけが詰まった自分だけの録音音声を作ることができる。テキストが老婆心からか妙な変換等を行っているために、こちらの使いにくいようになっているのであれば、それを使いやすいように変換するのみだ。
この手法をよく分析してみれば、これをインプロヴィゼーションの作業に逆応用することが考えられる。ノンイディオマティックなインプロにイディオマティックを導入することだ。二つのテリトリー間の往還をあえて導入すること。ノンイディオマティックとは一つのテリトリーにばかりとどまっていないことであることを考えれば、この戦術が妥当であると考えられる。また、ノンイディオマティックの複雑さを腑分けしていくるためにイディオマティックを用いてみること。
混沌としたものから特徴的なものを見つけ出すという絞り込みとでもいうプロセスがあってコトバは生まれたのではないか? つまり、ノンイディオマティックが整理されてイディオマティックとなる。ただ、イディオマティックはすぐに固定、保守化する。それゆえ、ノンイディオマティックで揺さぶりをかける必要がある。ただし、そのゆさぶりには「塩梅」が要る。
妄想的なイメージを使って言うならば、イディオマティックは時空を水平的に覆ってゆく。これに抗するための戦略はノンイディオマティックな個人的、垂直なものでイディオマティックな時空を穿つこと。垂直-自己以外のどこにもそれはなし。
毎回、何を随筆のように書いているのかと思われるかもしれないが、ワークショップを補うため、止むに止まれず、一つしかない自分の切り口で毎回書くことをひねりだしてきた。今まで書いてきた文章はワークショップを補完する要素であると同時に、それ自体が同じようなことを繰り返して述べつつも、何とか新しい見方なり側面を引き出し、より自分の言いたいことを、時にはすべてを言わず仄めかすにとどめ、時にはできるだけわかり易くするという試みの結果である。自分は音を扱う場合でも、こうした反復される、システマティックでない作業に興味がある。
人前でのインプロというのも、演奏日という締め切りまでああでもこうでもないと日々考え、試行錯誤しし、当日はそれまでに充填したものはあるにせよ、あらためてそれを白紙還元しナマでやっているが、その絞込みの過程がゆえ、それは純然たるインプロではない。人前での演奏の面白さは音楽というものが現在、色々なものにまみれており、それが見えるところにあると思う。ただ、それが全てではない。インプロ、演奏といったものは他の場所にもある。
このあとがきのようなニュアンスはなぜかと言えば、今後も引き続きひねくりだされるコトバはその出現場所を変えるからである。
解説のない野球放送のように。
次回のテーマ:起死回生のための「数」。
【 第7回目のワークショップの結果を受けて 】 … 村山政二朗
過度に腰を動かす仕事に就いているなら、できるだけ休養を取ることを考えるしかないが、そうでなければ、痛くても、少しでも動かすようにしたほうがいい。それはそうとして、その前にココロの問題だ、と。
本当に楽しいことがあると、それが痛覚を鈍らせ、椎間板ヘルニアに罹っていても腰痛にならない。痛みは頭で感じるのでそういうことになる。
腰を使わず生活することはありえないが、それをどう使っているかにはあまり意識が払われない。それを一つの身体の部分として捉え、動かせれば良いのだと、その有用性しか見ない。腰を器官の一つと言うのには抵抗があるものの、まあ「器官なき身体」(アルト-) ならぬ「器官あっての(物種よ的)身体」としてしまおう。部分の総合として全体があるという、機械論的有機的身体観について考えるために。
で、よくあるのは、ひとつのパーツが故障して全体が機能しなくなっているわけだから、全体の機能を回復させるためそのパーツを集中的に治そう、あるいは鍛えようとすること。一歩譲ってそれもありにしよう。ところが、ここで鍛えること自体の細部の中に、いやそれより前に、こうした事態にいかに対処するかということの中に、いろいろ面白い、あるいは重要なことがあるのにもかかわらず(ひとつの器官は鍛えられたが、それが他の器官とのバランスを崩すといったような。例えば、頭)、タカをくくって全てやっつけ仕事ですますという重大な欠点が、この有用性第一の身体観というか、世界観から生じる。
これはひとつの暴力、必要悪。まあそれも人間の特権よ(本能に従わないことができる)、と勝手に言わせておくにしても、実はそれを言ってしまったらおしまいでは? そして、そのおしまいのところからはじまるべき作業もあるはず。
有用性。「銭を得る仕事をしないで食えなかったらどうだというのだ?」みたいなことを言ったのは詩人の尾崎放哉だったか。何が最初に来るかという話。それはそうだが、「最初に来るものがあれば、カラダは動かしたいときには思うように動く」、これも半分だけしか賛成できない暴論。有用性、無用性のどちらかにとどまるよりは両方のあいだに通路をつけたほうが賢明では?
ここで停滞ということを考えてしまう。あたかも相撲の「死に体」のように、回復不能な固定した状態を受け入れる、そこにとどまり続けること。先入観に囚われ、そこに停滞すること。そうしないためにことばの梃子がいる。さもなくば停滞で充血で死体となる。
原因は自分の外にではなく内にあるのだ。
とは言いつつも、本能だけに従って生きる動植物の潔さを考えるに、それをしていないのは生物ではヒトだけらしいとなると、このヒト的事態をすべてサスペンドして動植物のように生きたいなあという逃げを打つ気持ちが出てくる。
森で鳥たちの囀りをよく聴いていると、その音が時空間の中でうまく配置されていると感じることがある。動物たちの、限られた空間を住み分けるという習性により、そんな事態になっているのかもしれないが、特に鳥の場合、そのノマド性は無視できない。
木々に留まりひとしきり鳴いたあと消え失せる。雲雀の中には何分もの間、羽ばたきながら空中に停止した状態で囀るのがいる。なんという潔さ。実情は、自分のテリトリーを確保するための必死のパフォーマンスといったところなのだろうが。なかにはしつこく、いつまでたっても鳴きやめないのもいる。
こうしたなかなかつかみどころのない鳥の生態から、こちらは彼らの内面で起きていることをあれこれ想像してみるだけだが、その空間内での囀りの、シェアリングの状態を、動きながら音を使ってシミュレーションしてみるのは面白いのではないかと思う。自意識のためか、時空間の音によるシェアが我々は下手なので。
「どう見られ、聞かれたいか」、と「どうやりたいか」をひとつの両極と考え、その狭間でサスベンドされている私にはそのうちの一極だけを選ぶことはできない。両方を天秤にかけた中央に私がいる。そんなイメージが私に生じたとたん全てはパーとなる。こんなふうに言いたくなる気もありますが、そして、そんなふうに求道者的に考えることも大事なのだろうとも言いたいですが、それだけでもないだろうということです。
実際問題として、現実的に、ある状況の中では、その前に少なくともすべきことがあるんではないか(困ったことに、この謂も落ち着くところは道の探求だ)?それをしないとそのある状況でなにかをやる意味がなくなってしまうから。ただ、それは言語化した途端にパーになってしまう、だからこそそれには言いようのない意味(道の代わりに未知を得る)があるわけなんですけども、残念なことにそれはコトバにしようがない。
余りにも意図が見え見えのものが多いというのはそういうことなのではないかと。意図が見えなさすぎて困る場合もあって、その時はこちらとの交感が作り出せない要因が何かあるか、向こうが本当にやりたいことが見えてないということなんでしょうから、タカを完全にはくくらないまでも、こちらもいちいち付き合っているわけにも行かず、適当なところですっぱり切り捨てておく。
そのときには付き合っている余裕はなくとも、事後的にその態勢に入る余裕は必要あらば自ずと出てくるわけですし。そうなると結局、そうタカをくくる余裕が既にこちらにあるかという話になってきて、と、こんなふうに考え続けると疲れて飽きてきて、出口なしで、困った困った、そろそろ何かそれに没入して自分を忘れられることはないかなと考える。
実はそのひとつとして音があったんだけれども。もとい。こんな往還の反復ということに結局はなるかと。
【 第6回目のワークショップの結果を受けて 】 … 村山政二朗
その目的が相手の興味を惹くことにあれば、成功するにはそれなりの工夫が必要となる。
とはいえ、これはヒトにとっては日常の茶飯事である。
サスペンスを仕掛ける意図が相手の態度から見え見えの場合、これに応じ、こちらからもサスペンスを与えることにより、状況をひとつのゲームとして楽しむこともできよう。ところが、そうした意図があるのか、ないのかわからないような狡猾な、あるいは間抜けなサスペンスに対しては、無力なこちらは宙ぶらりんの状態に置かれる、つまり、あるサスペンドされた事態を受け、その対応に困ったこちらがその状況自体をサスペンドするということがありうる。こうして日常の中に、いつの間にか非日常の次元が開けてゆく。さらには、日常の規範のサスペンドを標榜するような創造活動、その非日常的世界では、単なる日常的な行為がその非日常世界における非日常となり、ひとつのサスペンスたりうる。
日常-非日常という局面からサスペンスという事態を見てきたが、ここでインプロヴィゼーションとの絡みについて少し考えてみよう。一つの疑問はインプロヴィゼーションを非日常のものとし、日常生活とは別のことと割り切り、切り離してしまうのはどうなのかということである。
(インプロは日常を非日常化する。だから、インプロはインプロの日常も非日常化しなくてはならない。と同時に、インプロはすでに日常の中にある。生の充実は日常性と非日常性のダイナミクスの中にある。)
そう納めてしまった途端、つまり、日常-非日常の区分けをはっきりさせ、それぞれがカヴァーする範囲を決めた途端、この二極間に作り得る緊張は失われる(Aと非A。例えば、イディオマティックとノンイディオマティック)。もともと解りやすさを得るための方便として(本質をつかむために?)、二つの極に分節したのだが、確かに、ここから創造的な活用が見い出せよう。たとえば、日常なのか、非日常なのかのどちらか同定できなくなるまでに、両者がたえず入れ替わっているような、より高次のサスペンスの事態が想像可能だ。二分法によってこうした事態を創造活動において追求することを考えれば、これはホンマ、実用的な話である。
もとい。インプロヴィゼーションについて言えば、私見では、それを単に非日常のものとせず行うべしというのが建前であるが、本音は日常-非日常の区別をつけるというのも悪くはない、となる。特に、この活動を職業的に行っていない人には、インプロヴィゼーションの意義というのが、時間的にも限られた日常から非日常への移行により、生活にメリハリをつけることにあるだろうからだ。
補完し合う日常-非日常と、そうでない日常-非日常。
サスペンスには、唐突だが、ジョークや笑いも有効だ。それは緊張と弛緩というバランスに基づく。これも二分法。西欧文明有難う。我々は貴方の遺産を表層的にしか受容できなかった、それに気づいた今、改めてその本質を探るという道も取れようが、もうそんな悠長なことは言っておられなくなった、一挙に、極めて実際的、実用的なやり方で二分法を乗り越えるぞ、(これこそ堂々巡りの、表層的受容ならぬ、破れカブレの「能」容) と、意気込んだところで、すでに以上の事態に気づき、事を起こしている連中がむこうにはいるようで、西欧文明、これはなかなかアナドレニン。
以上、読み返しつつ、ベイリーの中期の演奏の組み立てを思い出した。ベイリーがベケットから影響を受けただろうことは想像に難くない。そういえば、ベケットには「ソロ」という声の作品がある。
次回のテーマは「身体と思考」

【 第5回目のワークショップの結果を受けて 】 … 村山政二朗
枠があるから変化に意味がある。
枠がないなら事情は異なるはず。
同様のことが日本人のお家芸といわれる「間」についても言えるのでは?
枠がないところでの「間」は間抜けになるのが不可避では?
どこで入り、どこで出るのか?それを決める基軸は何?
決断はそれが不可能であるからこそ決断となる。
要点を絞って喋る。簡潔に。言いたいこと、言うべきことを絞り込む。考えられたすべてから抽出された一部が現れる、それは一部であって、実は隠された部分、持続がある。その一部もそれが極限まで凝縮された状況では、それは意味として伝えるのが難しくなって、あるいは意味として伝えようとすること自体無意味になって、叫びとしてしか現れないかもしれない。それは論理的意味を越えてしまって、あるいは抽象度が高まりすぎて、意味不明の口ごもり、あるいは詩的な言動にしかならないかもしれない。いずれにせよ、出てきているのは一部。全て言ってしまったら実際、「いき」でなくなる。
今、自分が行っている最中のインプロヴィゼーションに対して、「こんなものでいいわけがない、ええい!」と出す音、動き、行為。
自分を、状況を、インプロヴィゼーション自体を叱咤するために。ただし、それが単なる自分の気持ちだけから出るのではなく。
ノン・イディオマティックなインプロヴィゼーションとは、インプロヴィゼーションのなかで起きていることの把握を第一に置き、それをもとにいかにインプロヴァイズするかの戦略をインプロヴァイズすること。
ここでいう戦略というものも、戦略であったりなかったりでありうる。インプロ自体もインプロであったりなかったりでありうる。
鳥が啼き止んだあとの静寂の緊張は、鳥がこちらからは見えない場所にいるとき、一層深まる。それは鳥の囀りを聴こうとする者により構成されるのだ。鳥には音楽をこちらに聞かせようという意図はない。かと言って、他の鳥の囀りが聞こえていないわけでもない。動植物、昆虫等々、驚くべき本能によってとてつもない調和を実現していることが、自然界で実際いろいろな例として知られているが、鳥たちもその囀りによって同じようなことをしているのではないか?彼らの行為はこちらの理解を越えているが、ある調和を実現しているのでは、と言ったら大げさであろうか?(事実はどうであろうと、こちらは実際のところかまわない) 未知の他者との遭遇に際してこちらにできるのは、連中の、あるかないかもわからない行動規範を想像し、そのリズムを近似し、それとともに振動、共鳴してみること。
反復としての行為、それによる行為の堆積性、その垂直性。
半分以上の時間が無音で行われる音楽がなかなか見つからないのは、行間の方が書かれた文章よりも大きい作品がなかなか見つからないのと同様の事情による。ここでマラルメが想起されるが、そのような作品の他に、彼には乗り越えそのものを謳った詩があり、それは同時に詩を乗り越えようとする姿勢なのだ。それはベイリーの74年頃のソロにも通じる。そのあたりのベイリーを否定する人たちは初期のラディカルな演奏の方をより評価するはず。ただそれらはまだ音楽の中にとどまっている。ないものねだりは必要だ。
次回のテーマは「サスペンス」。
【 第3回目・第4回目のワークショップの結果を受けて 】 … 村山政二朗
ただ、それを音に結びつけることは間違っていないのでは?「音楽の起源」のクルト・ザックスにはそれが見えている。
不可避な水平的な聴取をいかにやりくりするか。そのために垂直的な聴取はいかに可能か。
音楽の機嫌、期限、危言、奇現。
グレッグ・ブライト
「選択の不可避性を避けるためには、われわれは完全に流動的であらねばならない。「選ぶこと」も許されなければ、「選ばないことを選ぶこと」も許されない。この逆説に身を任せれば、速度と静止は同じ意味を持ち、限界のない調和が得られるだろう。」
枠があるから変化に意味がある。
枠がないなら事情は異なるはず。
次回のテーマは「変化」。
前回までの詳細はこちら
(Posted : 2013年05月14日)
トラックバックURL :
https://rrr666.net/archives/457/trackback








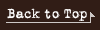
コメントを残す